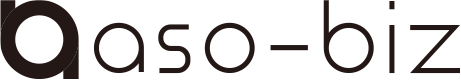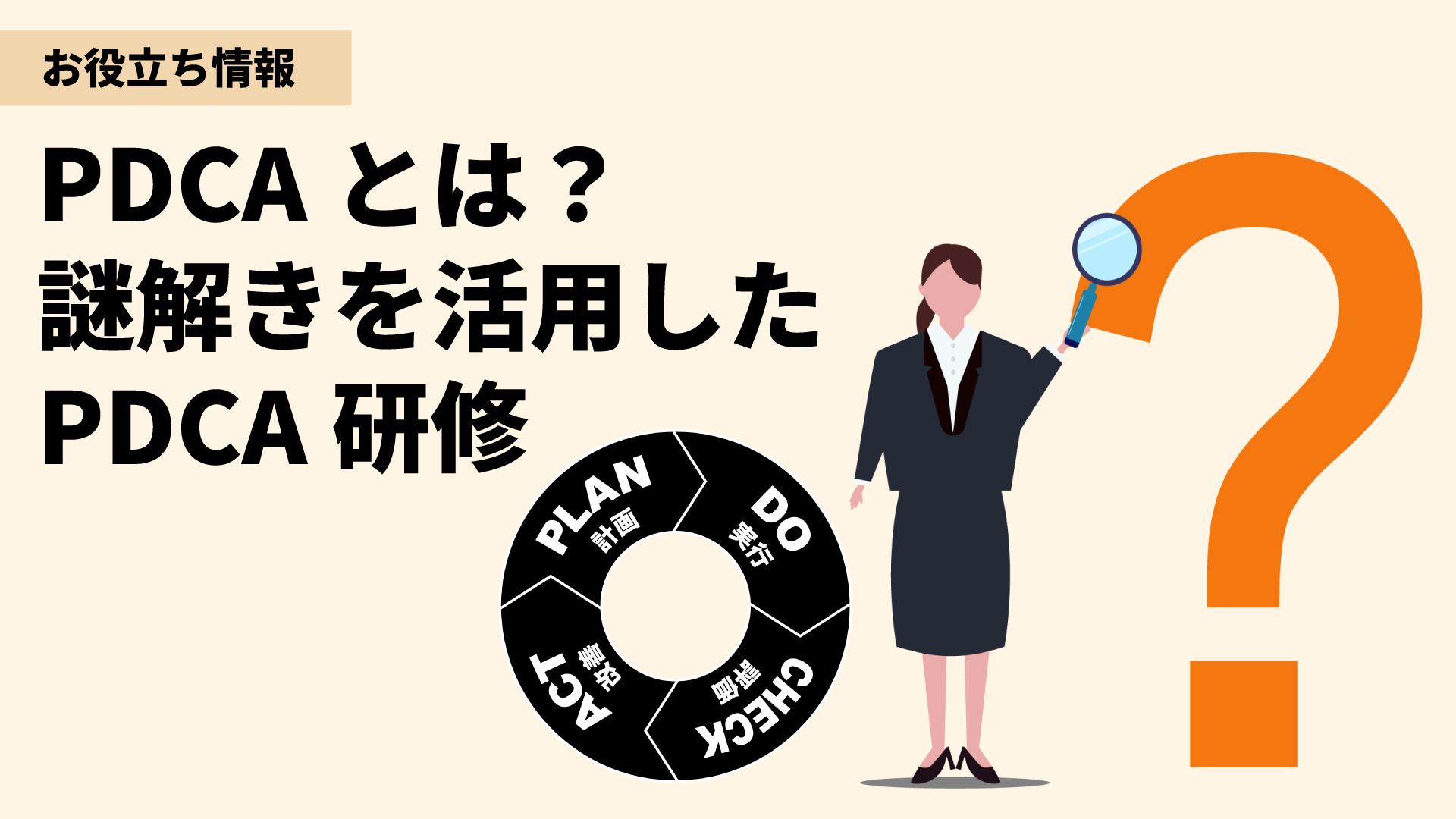
PDCAとは? 謎解きを活用したPDCA研修

-
柊
2025年10月28日
目次
この記事でわかること
まずPDCAの要点を簡潔に確認し、現場でつまずきやすい原因を3つに整理します。次に、短時間でサイクルを回すための設計例を提示し、締めくくりに当社の「謎解き×PDCA研修」の進行イメージをお伝えします。
PDCAとは
- Plan(計画):検証可能な仮説を“小さく”立てる。最初から精緻化しすぎない。
- Do(実行):分業して実行し、手順ログ(やった/やらなかった・所要時間)を残す。
- Check/Action(検証/改善):成果の良し悪しだけでなく“差分”を測り、次の一手を1つだけ具体化(担当・期日・想定効果まで言い切る)。
PDCAは“正解づくり”ではなく、“目標や理想と、現状の差分を狭め続ける”仕組みづくり。
なぜPDCAが回らないのか
1. 検証が遅い(単位が大きい)
月次・四半期の重い案件を前提にすると、Cが遅延して学習が起きにくい。結果が出る頃には条件も変わり、因果がぼやける。
2. 基準が曖昧(数値化できない)
“良くなった気がする”で止まり、C→Aが抽象化。優先順位が決まらない。
3. PとCが軽い(仮説づくりと検証設計が薄い)
Planで仮説・成功条件・測り方を決め切れていない/Checkが結果の感想に留まりがち。そのため差分と原因がぼやけ、Actionが「次に試す一手の確定」まで進みにくい。
私たちの謎解き研修では
私たちの謎解きPDCA研修では、ゲームでの実践+振り返りを2~3往復させ、受講者の実務にすぐ接続できる学習効果をねらいます。対象は新入〜中堅まで幅広く、PDCAの基礎定着/実務への置き換え/チーム内の主体的な発言をゴールに設計しています。
実施イメージ(プログラムの流れ)
- イントロダクション・アイスブレイク
狙いの共有、進め方の確認。 - 作戦会議(Plan)
チームでゲームの理解度をすり合わせ、進め方の仮説を立てる。 - 謎解きゲーム 前半(Do)
仮説に基づき実行。aso-bizが時間・試行を記録。 - 中間振り返り(Check)
前半の差分(想定と結果のズレ)を即時に言語化。 - 謎解きゲーム 後半(Action)
更新した仮説(改善)を即時実装して再度Do。防ぐ。 - 最終振り返り(Check)→結果発表→総括
効いた変更点を特定し、次の一手(A)を1つに絞って共有。
まとめ
- 回らない原因は「検証が遅い/基準が曖昧/PとCが軽い」*の3点に集約。
- 研修では、各工程に役割設計/ログ&即時フィードバックを組み込み、差分を縮め続ける運用習慣を体験的に獲得する。
- 題材としての「謎解き」は、明確なスコア・即時フィードバック・再試行を満たし、PDCAの“回る感覚”を安全に高速で得られる。
まずは小さく“回る”体験から。
目的・人数・時間に合わせて、研修プログラムをカスタマイズします。資料請求・お見積り・ミニ体験のご相談は、以下のフォームからご連絡ください。