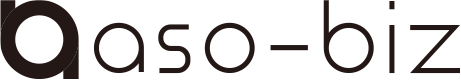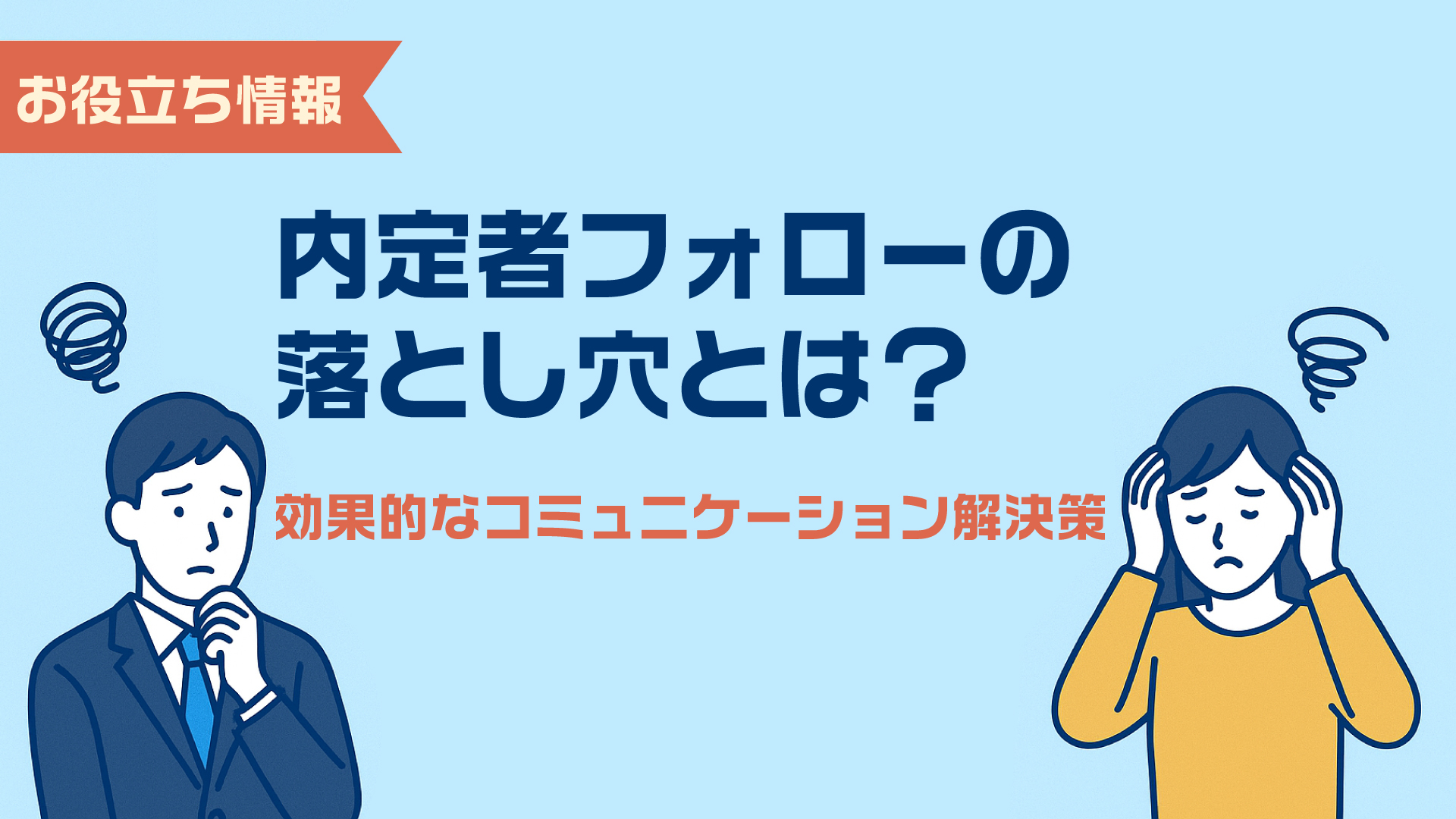
内定者フォローの落とし穴とは?効果的なコミュニケーション解決策

-
辰巳 麻耶
2025年11月11日
「内定を出したのに、入社前に辞退された」「内定者の温度感が読めない」──多くの採用担当者が直面する共通の課題です。
採用難の中、内定者フォローは“選考の延長戦”ではなく“入社後のエンゲージメント形成の第一歩”として、より戦略的に設計されるべきです。
しかしそのフォローが形だけだったり、コミュニケーションが一方通行だったりすれば、逆に離脱のきっかけになりかねません。
本記事では、内定者フォローで陥りがちな落とし穴と、効果的なコミュニケーション設計のポイントを解説します。
さらに、体験型研修で“対話と納得感”を生んできた aso‑biz の知見も交えて、実践的アドバイスをお届けします。
目次
よくある3つの落とし穴
① フォロー=イベント開催だと思っている
「懇親会」「グループワーク」など、接点づくりに偏ったフォローは少なくありません。
しかし、最近の内定者層(2000年代生まれ)は“仲の良さ”よりむしろ**「居心地・雰囲気・価値観の共感」**を重視しています。
形式的なイベントだけでは、彼らの“安心して関係を築ける場”としての効果が薄くなりがちです。
② 情報提供が一方通行になっている
「入社案内メール」「オンライン説明会」など、会社側から“伝える”だけでは、今の内定者層には響きません。
調査によると、ALL DIFFERENTによる2025年入社予定の内定者対象調査では、約51.2%が「内定期間中に先輩社員との関係構築の機会」を希望していることが明らかになっています。
この数字からも、内定者の“関わりたい/見てほしい”というニーズが高いことが読み取れます。
(引用:ALL DIFFERENT)
③ フォロー担当者の属人化
フォローが特定の担当者や部署に偏ると、温度差や“担当次第”という印象が出てしまいます。
担当者の経験や性格に依存しすぎると、フォローの質にばらつきが出ます。
特に複数部署・担当者で採用している場合、部署・担当間で温度差が生まれやすい点も注意が必要です。
フォロー体制を仕組み化し、共通の指針を持つことが、長期的な信頼構築につながります。
内定者フォローを“体験設計”として考える
1. 双方向コミュニケーション設計が鍵
今の内定者は、「何を話すか」ではなく「どう関わるか」を敏感に見ています。
具体的には、内定者同士がチームで課題に取り組むワークショップ形式が効果的です。
例えば、aso-bizの「謎解き研修」では、チームで“情報を共有/役割を担う/協力してゴールを目指す”という流れを設けています。
この構造を内定者フォローに応用すると、自然に“会話・関係・安心感”が育まれます。
2. フォローを“入社前成長ストーリー”にする
多くの企業が“点”としてフォローを行いがちですが、内定者には**“線”としての経験を設計**することが有効です。
例:
-
STEP 1:ウェルカムメッセージ+配属先先輩紹介
-
STEP 2:少人数グループワーク(価値観・期待の共有)
-
STEP 3:先輩社員との対話(リアルな仕事の話)
-
STEP 4:入社直前の確認会(期待値すり合わせ・不安解消)
このような流れを設けることで、内定者は「自分はこのチームの一員だ」という実感を早期に持てます。
3. “情報共有+感情共有”をセットで届ける
合理的なデータやメッセージだけでは若手の心は動きません。
たとえば、ALL DIFFERENTの調査では、内定者の約68.4%が「自分の能力で仕事についていけるか」に不安を感じていることが報告されています。
(引用:ALL DIFFERRENT)
この数字が示すのは、**「実感できるサポート」**がないと安心できない、という点です。
そこで、“先輩がどのように歩んできたか”“チームの雰囲気はこうだ”という感情的な共有も必要になります。
まとめ
内定者フォローは単なる“辞退防止”ではなく、**“入社後も共にスタートを切る関係性を育む場”**です。
形式的な連絡やイベントだけではなく、“対話”を軸にした体験設計が、若手人材の心を動かします。
aso-bizでは、そうした“遊びと学びを融合させた体験”を通じて、安心感・エンゲージメント・主体性を育てる内定者フォロー研修を提供しています。
さらに、プログラムを通じて内定者一人ひとりの適性やポテンシャルを把握することも可能です。 人事・育成担当者にとっては、入社後配属やフォロー計画の立案にも役立つというメリットがあります。
aso-bizのゲーミフィケーション研修の体験会では、実際にその効果を体感いただけます。
以下の日程で体験会を開催いたしますので、ぜひこの機会に奮ってご参加ください。
- 2025年12月2日(火) マーダーミステリー型研修体験会
- 2025年12月16日(火) ボードゲーム型アセスメント研修体験会
体験会にご参加できない方でも、簡単に資料をご覧いただけます。
ぜひお気軽にご相談ください。